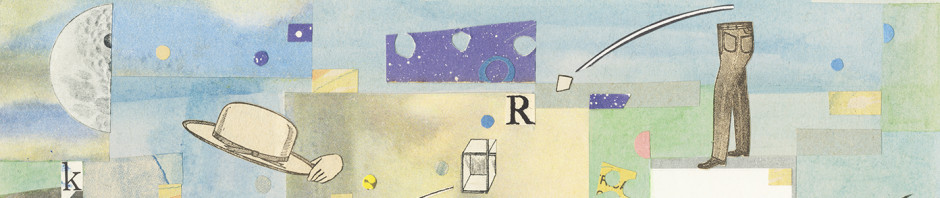十一月十六日、水曜日。大学生以来の町田にやって来た。LUMINEの九階にあるレストランに入り、案内された窓辺にある四人掛けの席に座った。窓の外に目を向けると、かすかに残った夕暮れの橙色が消えかけ、紺色に包まれた町田を見下ろせた。目に入るのはヨドバシカメラの大きな看板、沢山の無機質なマンションと数件のラブホテル。明かりのついた二階の窓からベッドを整える人の姿が見える。十数年振りに町田に来たのは、まほろ座で開催されるライヴ、小西康陽with矢舟テツロー・トリオ「小西康陽、小西康陽を歌う」を観るためだ。
午後七時から始まったライヴはもちろん『東京は夜の七時』から幕を開けた。一九八五年、自分が生まれたのと同じ年に結成されたピチカート・ファイヴの、都会に暮らす大人の音楽。愛知県に居たわたしにとって何処か遠い場所で輝いていたメロディに、今こうしてひとりライヴハウスに出向いて耳を傾けていることに幸福感が込み上げる。ライヴはそのあと『ゴンドラの歌』、『これから逢いに行くよ』、『あなたのことがわからない』、そしてこれは小西康陽さんご自身の声で歌っているのが一番いいじゃないか!!と興奮してしまった曲『そして今でも』へと続いた。それから『あんなに愛し合っていた二人なのに』、『動物園にて』と聴いているうちに、少し張り上げて伸びるときの声音や、リズムに乗った言葉がこちらにすっと伝わってくるイメージなど漠然としたことしか言えないのだが、小西康陽さんと坂本慎太郎さんの歌声の共通点をハッと感じた。矢舟テツロー・トリオの御三方が一旦ステージから去り、ソロの弾き語りが始まると、小西さんは心細そうに『連載小説』をぽつりぽつりと歌いはじめた。「映画の途中で フィルムが不意に途切れて」の歌詞で照明が落ち、小西さんの姿がパッと消え、数秒後に再び現れる演出に胸を打たれた。ドラムスの柿澤さんが加わると、小西さんはすぐにその場の指揮者へと戻り『face B』、『むかし私が愛した人』を歌ったあと、矢舟テツローさんがピアノで二曲披露した。わたしの座っている位置からは、矢舟さんが軽いタッチでピアノを弾く流麗な手元を堪能できた。それから小西康陽さん、コントラバスの鈴木克人さん、ドラムスの柿澤龍介さん、メンバー揃っての『不景気』を聴きつつ日本経済を憂い、微妙に歌詞を変えて歌っているNegiccoの『アイドルばかり聴かないで』に笑った。アイドルにも「ねぇ わたしを見てよね」より「己を見つめよう」と言われた方がグッとくると感じるのは、わたしがアイドルばかり聴いているおじさんではないからだろうか。そのあとは『悲しい歌』、『サンキュー』からの矢舟さんの軽快なピアノも最高な『陽の当たる大通り』。「一張羅のポケットの中 いつだってお金はないけど 陽のあたる大通りを アステアみたいに ステップ踏んで」歌詞のひとつひとつ、昔は聞いたことのある言葉だったものが、自分の生活の中にある言葉になっていったことを実感する。もうすぐライヴは終わってしまう、『グッバイ・ベイビイ&エイメン』でお別れ、しかし拍手は鳴りやまず、そのままアンコールの『マジック・カーペット・ライド』へ。そのとき、九年ほど前にヴァン・ダイク・パークスがビルボードでライヴをしたときのことを思い出した。それはそれは贅沢なコンサートだったのだが、最後に一曲だけヴァン・ダイク・パークスがソロでピアノを弾いた。すると会場の空気が一変し別世界のようになった。この演奏を聴くために今夜私達はここに来たのだと感じた。小西康陽さんのソロも、そんな特別さがあった。帰り際、同じ会場に居た二人組の会話が耳に入った。
「今日も最高だったね」
あの人たちは先週土曜のライヴにも行ったんだな。
「でも前回はさ、アレが聴けたんだからねぇ」
アレ?アレとは何だろう。
ライブの余韻に浸りながらの帰路、満たされた気持ちの中でまたアレが気になりだす。翌日、土曜のライヴはまだ配信されていた。これは確認しないわけにはいかないと視聴した。わたしが見たライヴよりもずっと緊張されているように感じた。終盤アンコールで歌う『私の人生、人生の夏』に聴き入る。なんていい曲なんだろう。わたしが知っているのは、名画座でお見かけする小西康陽さんの姿だけだが、この曲は正に現在の小西さんが歌うべき曲なのではないだろうかと、感涙してしまった。しかしなぜかこの曲を昨夜聴いた記憶がなくなっている。そして最後にピアノに向かい『マジック・カーペット・ライド』を歌いはじめた。
表現する場があることを特権だと言う人がいるけれど、表現するということは、同時に恥をかく覚悟と切り離せない。何かを好きでいる気持ちを忘れられず、表現し続けてきたひとの歩んできた時間を目の当たりにしたような思いで、打ちのめされた。小西さんの眼から堰を切ったように溢れだした涙の理由は、わたしの知らないものだ。きっとこれから何十年も先に分かるかもしれないもの。コンサートの主役のように、才能ある人たちの中心に立ち、観客の拍手喝采を浴びることはできなくとも、それでも音楽や映画や本や人を好きでいることを、表現することを、それを誰かに見てもらうことをやめないでいたら、あの涙を身をもって知ることができるかもしれない。そんなライヴに居合わせることができたことを心から誇りに思った。